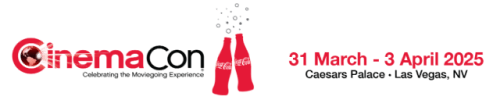シネマ業界最大の恒例イベント CinemaCon 2025 が米国ラスベガスで開催されました。 昨年(CinemaCon 2024)の報告に続き、本会合の状況を総括します。
目次
NATO 改名 => Cinema United
これまで CinemaCon は、米国映画館オーナーの組合である NATO(全米劇場主協会)の主催で開催されてきましたが、長年、もう一つの NATO(北大西洋条約機構)と混同され続けてきた状況を解消すべく、本年の CinemaCon を機に、団体名が Cinema United(シネマ連合)へと改名されました。

Cinema United は、”Moviegoing is our mission”、
日本語に訳すと
『映画館で映画を観せること、それが私たちの使命です。』
をモットーに掲げています。
全米劇場主協会という名称と比べると、参加企業の実態がやや見えにくくなった印象もあるかもしれませんが、”Moviegoing is our mission” という言葉によって、劇場興行を推進する団体であることがより明確に伝わるようになりました。
初めて参加する人にも、シネマ業界の連合が主宰していることがひと目で分かるようになったのではないでしょうか。
これで少なくとも、北大西洋条約機構と混同されることはなくなるでしょう。
主催と協賛
CinemaCon は Cinema United (シネマ連合) 主催のもと、
- ICTA (国際シネマテクノロジー協会):<= 私が加盟する団体
- 映画館で使用される機器の技術開発、製造、運用に携わる企業を中心とし、映画産業における技術の進歩を促進する団体
- NAC (全米コンセッション協会):
- 劇場運営に関わる飲食、売店、その他関連商品、サービスを提供する企業を中心に構成される団体
の協賛で開催されています。
スポンサー企業
スポンサー企業には業界ではお馴染みの企業が名前を連ねますが、開催年によって新規参入から事業撤退まで微妙に入れ替わりがあり、各企業の力の入れ具合、勢いの変化が感じられるのも面白いところです。
スタジオパートナー
上映作品の提供や監督、俳優などを呼び入れて新作映画の紹介をしてくれるのがスタジオパートナーです。
特別登壇ゲスト:(シネマ技術とは無関係ですが。。)大劇場 The Colosseum Theater で行われた計9回のプレゼンテーションの中から、特に印象に残ったゲスト登壇を紹介します。
- トム・クルーズ:自身の新作紹介に先立ち、急逝した『トップ・ガン』以来の友人ヴァル・キルマー氏を偲び、観客と共に黙祷を捧げました。心よりご冥福をお祈りします。
- サム・メンデス:伝説のロックグループの各メンバーを描く伝記映画4作品を2028年に同時公開する計画を発表。観客一同大興奮でした。
常連の大手スタジオに変動はありませんが、コロナ禍以降参加を見送ってきた Amazon が MGM 買収後、再び戻ってきました。
一方、映画館での興行から距離を置くネットストリーミング系大手が参加に動く気配はありません。
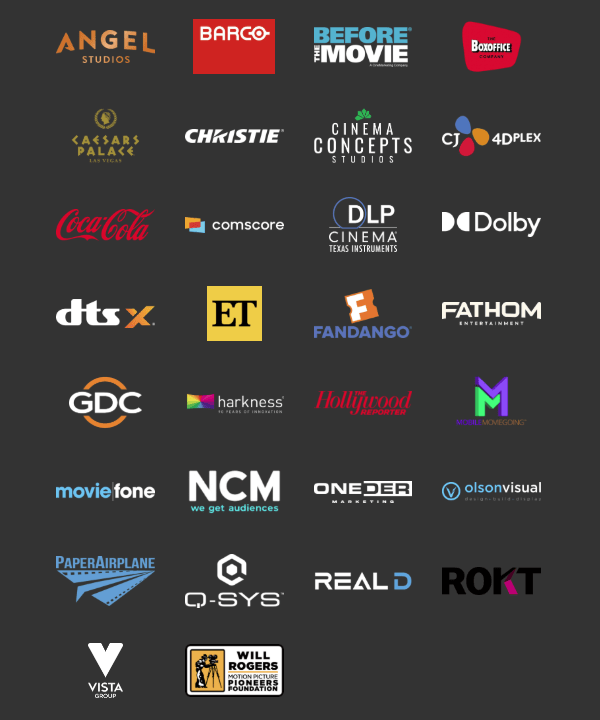
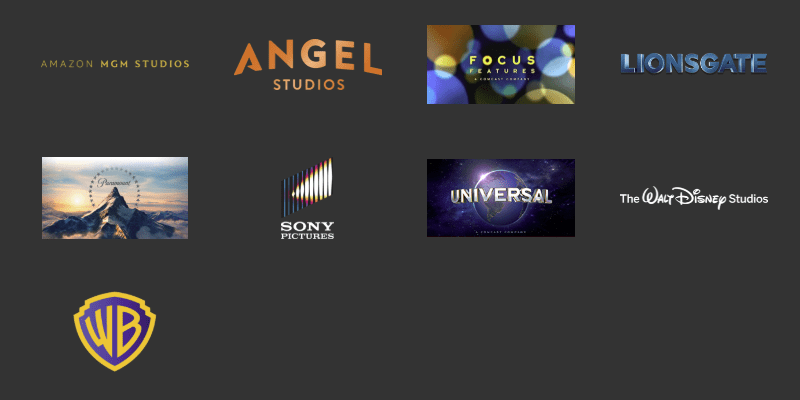
企業出展状況
昨年は、ほぼコロナ禍前の活況を取り戻したように感じられましたが、今年はやや様子が異なっていました。
個別企業の出展ブースが並ぶボールルームでは、ブースの数がピーク時のおよそ 2/3 程度に減った印象を受けました。大きく空いたスペースには、来場者が打ち合わせなどに利用できるテーブルが多数設置されていました。
一方、企業ごとのプライベートルーム出展は、ピーク時と同程度の規模が維持されていたように見受けられました。
なお、これらはあくまでも私自身の印象に基づくものであり、実際に数を正確に確認したものではないことをお断りしておきます。
各種技術デモンストレーション
The Colosseum Theater での HDR 上映
これまで、会場ホテルであるシーザースパレス内の大劇場 The Colosseum Theater には、Dolby Cinema の上映機材が設置されてきましたが、今年は新たに HDR by Barco 仕様の機材も導入され、デモコンテンツの上映が行われました。
いずれも仮設設備にも関わらず素晴らしい映像を実現していましたが、デモコンテンツを見ただけで両者の違いを言い当てるのは困難で、最早一般的な観客にとっては、ブランド名の違いしか意味を持たなくなっているのかも知れないと感じさせられました。
LED シネマ(直視型シネマディスプレイ)〜 DCI 新規格対応に向けた動き
今年に入って、DCIの新規格(HDR上映規格および直視型シネマディスプレイ規格)に基づく認証試験に合格した機材が登場しましたが、当該機種による HDR デモを見ることはできませんでした。
一方、直視型シネマディスプレイの先駆けとして8年前から製品展開を続けてきた Samsung は、DCI の HDR 規格に定められた最高輝度 300 nit のデモを実施しました。今回の CinemaCon 開催時点では、まだ DCI 新規格に基づく正式な認証は取得していないものの、その実力を十分に感じさせる内容でした。
ただ、今日普及している Dolby Cinema の約3倍に相当する最高輝度は、圧倒的な迫力で目を刺激するレベルに達しており、上映作品や鑑賞スタイルによっては、観客に不快感や苦痛を与えうることを改めて実感させられました。実際の映画上映においては、この輝度をどのように活かすか、その運用の難しさをも予感させるものでした。
音声透過型シネマディスプレイ
直視型シネマディスプレイにおける重要な課題の一つとして、前方からの音響をいかに再現するかという問題が認識されています。
この課題に対する一案として、音声透過型シネマディスプレイのモックアップ展示が行われました。
これは、シネマサーバーメーカーとして知られる GDC が、LED ディスプレイを取り扱う Tricorne 社と共同で検討を進めているもので、LED 素子が配列されている基盤部分に切り込みを入れ、その隙間部分から背面のスピーカーからの音声を透過させる仕組みになっています。


今回は実際に動作するデモではなく、構造上のサンプルを示す展示に留まっていたため、性能的な評価はできませんでしたが、アイデアとしては興味深いものでした。
モックアップ展示を見て特に気になったのは、LED がマウントされている基盤部分に相当数・広範囲の穴を開けることで、音声が通過する際に共振などの悪影響が生じないかという点でした。
いずれにせよ、興味深いアプローチであることに変わりはなく、今後の進捗を注視していきたいと思います。
クローズドキャプションおよび音声ガイド送受信機器
デジタルシネマのコンテンツパッケージ DCP には、上映に際して必要なすべてのデータをまとめてパッケージ化することができます。
その中には、一部の観客にだけ必要とされるクローズドキャプションや音声ガイドのデータも含まれており、必要とする人に対してだけ再生する仕組みがあります。
クローズドキャプションや音声ガイドを再生する機器は数社から提供されていますが、今回、Dolby の製品が更新されているのを見つけました。




クローズドキャプションや音声ガイドを利用する方が、映画上映中に座席のカップホルダーに設置して使用するもので、受信端末は大きめのスマホ大で、キャプションを表示するディスプレイと音声を出力するヘッドホン端子が付いています。
ディスプレイのプライバシースクリーンの性能は高く、ほぼ利用する本人にしか画面が見えず、隣席や後部席の人の視界に入りにくい設計になっていました。
DCP にクローズドキャプションや音声ガイドをパッケージする方式は、デジタルシネマの標準規格に準ずるもので、世界中の多くの国々で使用されています。
しかし、残念ながらこの方式は日本では使用されていないのが現状です。
国内の業界には、今後の積極的な対応を期待したいところです。
参考資料:Dolby Accessibility Solution
技術セミナー:映画興行における AI 活用
ICTA 主催の技術セミナーに、
“AI in Exhibition: Transforming Technology and Operations”
という、今どきのテーマに沿ったタイトルのものがあったので参加してみました。
多くの産業分野と同様に、映画興行の分野でも AI による恩恵が期待されています。
観客が受ける価値をさまざまな角度から向上させるとともに、劇場運営の効率化、収益向上、新たな価値の創出など、多様な可能性が語られていました。
その一方で、AI によって雇用機会が奪われるリスクについても言及されました。
それに対してあるパネリストは「AI はあなたの仕事を奪わない。AI を使いこなす誰かがあなたの仕事を奪うかもしれない」と答えました。
どこかで耳にしたようなやりとりですが、改めて考えさせられるものがありました。

CinemaCon 新たなイベントの試み 〜 Cinema Systems Summit
シネマ技術と運営に関わる業界団体 (InterSociety / ISDCF / ICTA / Cinema Foundation) の協賛により、CinemaCon 初日の新たな試みとして Cinema Systems Summit が開催され、今日のシネマ体験を支える様々な技術課題について発表と議論が行われました。
デジタルシネマの黎明期には、SMPTE 主催による Digital Cinema Summit が、映像技術やコンテンツ技術に特化した恒例イベントとして NAB で開催されていましたが、デジタルシネマ技術の成熟に伴い、開催されなくなってしまいました。
今回のサミットでは、デジタルシネマの中核技術が成熟した現在、よりシステム運用、周辺技術、顧客体験など、映画館ビジネス全体に裾野を広げたテーマが取り上げられました。
主催も技術標準化団体から業界団体へ、開催場所も NAB から CinemaCon へと変わり、新たなスタイルでの開催となりました。
半日余りのイベントで取り上げられた話題について、私の主観も交えつつ以下にまとめます。
劇場設備の活用方法
劇場設備をフル稼働させるための上映作品が不足している。多目的利用可能なスクリーンの導入など、映画館を複合施設化する事例もあり。
社内技術チーム vs. 社外サービス
映画館は社内技術チームを持つべきか、社外サービスに任せるべきか。ある大手映画館チェーンでは、自社チームの方が効果的だったとの報告。劇場規模によってはアウトソースの方が効率的な場合もある。
コンテンツネットワーク保護
サイバーセキュリティの重要性が高まっている。デフォルトパスワードのまま運用されていたシステムがマルウェアに感染した事例も。TPN が自己評価ツールを提供しているとのこと。
『アバター3』技術概要
『アバター2』とほぼ同様。3D、HFR、HDR への対応、そして30種類以上の異なる画像バージョンが作成される見通し。
DCP 名前付け規則 (DCNC) のほぼすべてのバリエーションが作成されることになるのかも。
LEDシネマディスプレイ導入の是非
LEDスクリーンの設置に関する課題や顧客への利点、潜在的な欠点が議論された。特に音声品質への懸念と、コストが大きな障壁となっている。
劇場技術の顧客訴求
映画や劇場のマーケティング環境の変化は激しく、ソーシャルメディアが顧客を惹きつける重要なツールとなっているとのこと。
特定の上映技術に関心を持つ客層も確実に存在しており、各劇場が持つ技術的特徴をより効果的にアピールすることが、今後ますます重要になると感じた。
以上、本稿では触れきれなかった内容については、また別の機会にご紹介できればと思います。
CinemaCon 2026
次回 CinemaCon は 2026年4月13日〜16日 という日程で開催される予定です。これから一年間の進展を注視しながら、次回を楽しみにしたいと思います。